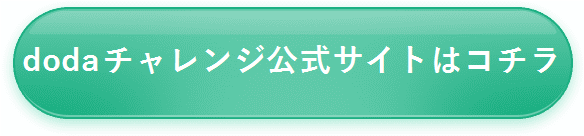dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や断られる人の特徴について解説します

dodaチャレンジを利用しようと思って登録したのに、「サービスの対象外だった」「求人を紹介してもらえなかった」といった経験をされる方も一部いらっしゃいます。実際には、dodaチャレンジが対応できる範囲や求人内容には一定の条件があるため、すべての人に求人がマッチするとは限りません。ここでは、なぜdodaチャレンジで断られてしまうケースがあるのか、その理由や断られやすいとされる特徴について解説していきます。
まず多いのが、「障がい者手帳が未取得で、申請予定もない」というケースです。dodaチャレンジの求人の多くは障がい者雇用枠に該当するため、手帳がない場合は求人紹介が難しくなることがあります。また、働ける時間が非常に限られていたり、医療的ケアが日常的に必要な場合なども、紹介できる求人の数が少なく、結果としてマッチングが難しくなることがあります。
さらに、「希望条件が極端に狭い」「正社員・高年収・在宅限定」などの条件が重なっている場合、紹介できる求人が一時的に見つからないこともあります。これはサービス側の意向というよりも、求人市場の現実的なバランスによるものです。そのため、希望を少し広げたり、柔軟に相談を重ねることで、次第に道が開けてくるケースも少なくありません。
断られたからといって、自分を否定されたと感じる必要はありません。一時的に条件が合わなかっただけ、という場合もありますし、状況が変わればまた利用できる可能性もあります。まずは理由を確認し、必要であればアドバイザーに相談してみることから始めてみましょう。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
dodaチャレンジでは、一人ひとりの希望に合わせて最適な求人を紹介することを大切にしていますが、場合によっては「現在の条件ではご紹介できる求人が見つかりません」と案内されることがあります。これは、利用者側に問題があるというよりも、市場に出ている求人とのマッチングが難しい状態であることが多いです。特に希望条件が非常に細かい場合や、勤務スタイル・職種・勤務地に強いこだわりがある場合は、条件に一致する求人が限られてしまい、結果的に紹介が難しくなるのです。条件が厳しすぎると、選択肢が狭まるだけでなく、求人が出たタイミングを逃してしまうこともあります。まずは自分の希望と市場の状況をすり合わせながら、少し柔軟に考えてみることも大切です。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
「在宅勤務限定がいい」「フルフレックスがいい」「年収は最低でも500万円以上ほしい」など、働き方や条件に強い希望がある場合、そのすべてに一致する求人を見つけるのは現実的にかなり難しくなります。特に障がい者雇用枠の求人では、まだ在宅勤務の導入率が一般の求人ほど高くない企業も多く、制度として整っていてもポジションが限られていることがあります。また、年収が高めに設定されている求人は、求められるスキルや実務経験も相応に高いことが多く、結果として条件が合わないことがあります。希望を持つことは大切ですが、どこを優先したいのか、どこなら譲れるのかを整理して、相談しながら現実的な条件に調整することで、紹介できる求人の幅が広がる可能性があります。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
「デザインだけに絞って探したい」「音楽や映像の仕事がしたい」といったクリエイティブ職やアート系などの専門職を希望する方は、求人の絶対数が少ないことから、マッチングが難しくなる傾向があります。こういった分野は、障がい者雇用枠としての求人があまり出回っていないため、タイミングによっては全く紹介ができないこともあるのです。また、企業側も障がいへの配慮と専門スキルを両立できる環境を整えるのが難しく、採用自体が限定的になることもあります。どうしてもその職種にこだわる場合は、時間をかけてチャンスを待つ必要がありますし、まずは事務職やサポート業務などを通じてスキルや経験を積んでから再挑戦するのもひとつの方法です。長期的な視点でキャリアを見つめ直すことが大切になります。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
地方に住んでいて「できれば地元で働きたい」「引っ越しは難しい」と考える方にとっては、そもそも求人の数が少ないという現実的な課題があります。都市部に比べて、障がい者雇用を積極的に行っている企業の数が限られていたり、そもそも企業自体が少ないエリアも多いため、紹介可能な求人が極端に少なくなってしまうことがあります。また、通勤手段の問題や勤務形態の柔軟さが求められることで、条件に合う企業はさらに絞られる傾向があります。こうした場合は、リモートワークの選択肢や、近隣エリアまで範囲を広げて検討してみることもひとつの方法です。アドバイザーに「通勤できる限界の範囲」や「働き方の希望」をしっかり伝えたうえで、現実的なマッチングを目指すことが大切です。
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジは、障がいのある方に特化した転職支援サービスとして、多くの方に活用されていますが、中には「申し込んだけれどサポート対象外と判断された」というケースもあります。これは個人の能力や意欲が否定されるという意味ではなく、あくまでdodaチャレンジが提供するサービスの性質上、対応が難しいと判断される場合があるということです。たとえば、障がい者雇用枠での求人を希望しているにもかかわらず、障がい者手帳を持っていない場合や、就業継続の見通しが立ちにくい場合などは、紹介できる求人や支援の方法が限られてしまうため、別の支援機関の利用を勧められることがあります。こうした判断はすべて、求職者にとって無理のない選択をしてもらうための配慮であり、他のステップへの橋渡しでもあるのです。
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠」での求人紹介は、原則手帳が必要)
dodaチャレンジで紹介される求人の多くは、「障がい者雇用枠」に該当するため、原則として障がい者手帳を保有していることが前提となっています。手帳がないと、企業との採用条件が合致せず、紹介自体が難しくなるケースがほとんどです。そのため、障がい者手帳をまだ持っていない方、もしくは取得の予定がない方については、サポート対象外と判断されることがあります。ただし、「現在手帳を申請中」「これから取得予定」という方であれば、面談や相談を受けられることもありますので、まずはその旨をアドバイザーに伝えるのがよいでしょう。場合によっては、手帳取得のサポートや必要な情報も教えてもらえることがありますので、迷っている場合も一度相談してみることをおすすめします。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
過去に就業経験があまりない、あるいは長いブランクがあって働く感覚に不安があるという方も、dodaチャレンジではサポートの可否が個別に判断される場合があります。たとえば、社会人経験がまったくない状態でいきなりフルタイム勤務を希望する場合、企業とのマッチングが難しく、実際に紹介できる求人が極端に少なくなることもあります。そのような場合、まずは短時間勤務から始められる仕事や、働く準備を支援する別の制度(たとえば就労移行支援)を案内されることもあります。これは本人に無理をさせず、段階的に就労に向かうためのステップとして設けられているものです。「いきなり働くのは不安だけど、何か始めたい」という方は、まず支援の選択肢を広げてみるとよいかもしれません。
状が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
精神的・身体的なコンディションが安定しておらず、定期的な通院や体調の波が大きい場合などは、「現時点では一般就労はまだ難しいかもしれない」と判断されることがあります。その場合、いきなりdodaチャレンジでの求人紹介を進めるのではなく、まずは生活リズムを整える、就労準備を行うといった支援を受けることを優先するよう勧められることがあります。たとえば就労移行支援事業所などでは、職業訓練や模擬就労、ビジネスマナーの習得などを通じて、段階的に働く準備ができるようになっています。dodaチャレンジでも、必要に応じて信頼できる支援機関を紹介してくれるので、いきなり断られたと感じるのではなく、「今は準備の期間」と受け止めて、次のステップへとつなげていくことが大切です。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
dodaチャレンジでは、初回の面談がとても大切なステップとされています。これは就職活動の選考ではなく、あなたの状況を整理し、最適な求人や働き方を一緒に考えるための時間ですが、準備が不十分なまま面談に臨んでしまうと、アドバイザー側があなたに合った求人を探しきれず、結果として「ご紹介できる求人がありません」となるケースがあります。たとえば、自分の障がいの特性や、どのような配慮があると働きやすいのかが説明できない場合、企業とのマッチングに支障が出てしまいます。また、「どんな仕事がしたいか」「これまでどんな経験があるか」が明確でないと、紹介すべき求人の方向性が定まらないため、マッチングの精度が下がってしまうのです。面談前に、簡単でもいいので自分の希望や働き方のイメージを整理しておくことが大切です。
障がい内容や配慮事項が説明できない
面談の場では、「どういった場面で困りやすいか」「どんな配慮があると働きやすいか」といった点について必ず聞かれます。これは企業に対して正確に情報を伝え、あなたに無理のない職場環境を整えるための大切な質問です。しかし、自分でもまだ障がい特性について整理できていなかったり、何をどう伝えたらよいか分からない場合、アドバイザーも企業側にうまく共有できず、結果的にマッチングが難しくなることがあります。正解を求められているわけではないので、感じている困りごとや過去の経験をもとに、話せる範囲で構いません。たとえば「音に敏感で静かな環境が合う」「通院で週に1回早退が必要」など、小さなことでも具体的に伝えることで、適した求人が見つかりやすくなります。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
「できれば働きたいけど、どんな仕事がいいか分からない」「とりあえず何でもいい」といった曖昧な姿勢のまま面談に臨むと、アドバイザーとしてもどの方向で求人を探せばよいのかが分からなくなってしまいます。もちろん、最初から明確なキャリアプランがなくても大丈夫ですが、「事務職が気になる」「以前は販売をしていたので、それに近い仕事なら安心」など、少しでも興味や経験に基づいた方向性を共有しておくとスムーズです。また、「週何日働きたいか」「通勤時間の上限」などもあわせて整理しておくと、より現実的な提案が受けられます。将来のビジョンを明確にすることは、自分自身の自信にもつながりますし、就職活動全体が前向きな流れになります。
職務経歴がうまく伝わらない
職歴がある方でも、「何をどのようにやっていたか」がうまく伝わらないと、アドバイザーがあなたの強みを把握できず、適切な求人を紹介するのが難しくなります。「ただ働いていただけで特別なことはしていない」と感じるかもしれませんが、日々の業務の中にも必ずアピールできる要素はあります。たとえば「Excelでのデータ入力を正確にこなしていた」「接客でクレーム対応も経験した」など、具体的なエピソードがあるだけで、職務内容に説得力が出てきます。事前に履歴書や職務経歴書を作っておくと、面談もスムーズになりますし、自分の経験を振り返るきっかけにもなります。アドバイザーはあなたの過去の経験をもとに、強みを引き出してくれる存在なので、できるだけ詳しく伝えることが大切です。
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
dodaチャレンジは全国対応の転職支援サービスですが、実際に紹介できる求人の数は地域によって偏りがあります。特に地方エリアにお住まいの方で「近隣で働きたい」「引っ越しは難しい」といった事情がある場合、条件に合う求人が見つかりにくくなることがあります。また、通勤が困難な事情から「完全在宅勤務のみ」を希望している方にとっても、対象となる求人は限られてくるのが現状です。これはdodaチャレンジ側の問題ではなく、地方での障がい者雇用枠自体が少ない、または在宅勤務制度が十分に整っていない企業が多いという社会的な背景によるものです。リモート勤務が広がってきたとはいえ、全ての職種や企業に適用されているわけではないため、希望を絞りすぎるとマッチングのチャンスを狭めてしまうことにもなりかねません。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
北海道・東北・四国・九州など、都市圏から離れたエリアでは、障がい者雇用に積極的な企業の数がどうしても少なくなる傾向があります。特にITやクリエイティブ系など都市部に集中しがちな職種では、地方での求人が見つかりにくいという課題があり、「地元で働きたい」「実家から通いたい」と希望する方にとっては、求人の選択肢がかなり限定されてしまうのが現実です。dodaチャレンジとしても、オンラインでの面談や地方求人の開拓に力を入れてはいますが、求人数そのものが少ない場合には、希望に合う仕事をすぐに紹介するのが難しいことがあります。一方で、通勤に無理がなければ隣県まで範囲を広げたり、在宅と出社を組み合わせた求人を検討することで、選択肢が増える可能性もあります。地域にこだわりすぎず、柔軟に考えてみることが大切です。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
働き方の多様化が進み、在宅勤務を取り入れている企業は増えていますが、「完全在宅勤務のみ」を希望する場合は、dodaチャレンジで紹介できる求人が限られてくる傾向にあります。特に地方に住んでいて、地元に求人が少ないからこそ在宅勤務を望むという方は少なくありませんが、企業側がまだ出社を前提とした勤務体制である場合、マッチングが成立しにくくなってしまいます。また、在宅勤務可の求人であっても、最初の研修は出社が必要だったり、定期的な出勤を求められるケースもあるため、完全に出社なしという求人は一部に限られます。「どうしても通勤が難しい」という事情がある場合は、アドバイザーに率直に伝えたうえで、在宅に対応可能な業務や企業があるか相談してみることが大切です。同時に、通勤の範囲を少しだけ広げたり、部分在宅の求人も視野に入れると可能性が広がります。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
dodaチャレンジでは、障がいのある方が安心して働ける職場を見つけるために、正確な情報をもとに求人を紹介する仕組みが整っています。そのため、登録時の情報が事実と異なっていたり、不備がある場合には、残念ながらサポート対象外と判断されてしまうことがあります。たとえば、障がい者手帳を取得していないにもかかわらず「取得済み」と記載してしまったり、働く準備が整っていない状態なのに「就業可能」としてしまうと、企業との信頼関係にも関わるため、サービス継続が難しくなることがあるのです。また、職歴やスキルに誤りがある場合も、求人紹介後のミスマッチやトラブルの原因になるため、アドバイザー側が慎重にならざるを得ません。登録時には「うまく見せよう」とするよりも、正直に現状を伝えることが、良い結果につながる第一歩です。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
dodaチャレンジが扱う求人の多くは障がい者雇用枠での採用となっており、企業側も「障がい者手帳の所持」を選考条件にしているケースがほとんどです。そのため、手帳が未取得の状態で「取得済み」と登録してしまうと、企業との信頼関係に影響する恐れがあります。たとえ悪意がなかったとしても、後から判明した場合は求人紹介が停止されたり、最悪の場合はサポート対象外となってしまうこともあります。ただし、「現在申請中」や「取得予定がある」場合であれば、その旨を正直に伝えれば柔軟に対応してもらえるケースもあります。ごまかしたり背伸びをするよりも、今の状況をそのまま伝える方が、結果的にスムーズに進められることが多いのです。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
体調や生活リズムがまだ整っていなかったり、主治医から「就労はもう少し様子を見た方がいい」と言われている段階であっても、「早く働かなくては」と焦って登録してしまう方もいます。気持ちはとてもよく分かりますが、実際に働き始めた後に不調が出てしまうと、本人にも企業にも大きな負担になってしまいます。そのため、面談の中で「今はまだ働く準備が整っていない」と判断されると、サービス利用を一時見合わせるよう案内されることがあります。これはネガティブな意味ではなく、あくまで本人にとって無理のないタイミングを見計らうための配慮です。dodaチャレンジでは、就労移行支援など他のサポート機関との連携もしているため、必要に応じて次の一歩につながるアドバイスも受けられます。
職歴や経歴に偽りがある場合
職務経歴やスキルの情報に事実と異なる点があると、求人の紹介や企業との面接に大きな影響が出てしまいます。「少しだけ盛ってしまった」「空白期間を隠したかった」という場合でも、選考が進んでから事実が判明すると、企業からの信頼を損ねるだけでなく、サポート自体の継続が難しくなるケースもあります。アドバイザーは、あなたの経験や強みをできる限り引き出し、整理してくれる存在です。だからこそ、誤魔化すのではなく、「ブランクはあるけど今はやる気がある」「前職で苦労したけど学びもあった」など、等身大の情報を伝えることが大切です。正直なやり取りの中からこそ、本当に自分に合った仕事との出会いが生まれるものです。勇気を出して、自分の今をありのまま話してみてください。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
「dodaチャレンジを使って応募したのに断られた」と感じてしまう方の中には、実際にはdodaチャレンジ側からの判断ではなく、企業側の選考結果であることも少なくありません。つまり、求人紹介や書類提出まで進んだうえで、その先の面接や書類選考で不採用になるというケースです。これらはあくまで企業の採用基準による判断であり、dodaチャレンジのサービス内容やアドバイザーの対応とは切り離して考える必要があります。しかしながら、気持ちの上では「dodaチャレンジを使ったのにうまくいかなかった」と感じてしまうのも自然なことです。大切なのは、落ち込んで終わるのではなく、「なぜ不採用だったのか」「次に活かせることは何か」をアドバイザーと一緒に振り返りながら、次のチャンスにつなげていく姿勢です。就職活動は一回で決まるものではないからこそ、過程そのものを学びにしていくことが重要です。
不採用は企業の選考基準によるもの
不採用となった場合、その理由は企業ごとにさまざまですが、多くは「他の候補者との比較」「求めるスキルとのミスマッチ」「社内体制との相性」など、あくまでその企業の採用方針による判断です。中には「とても良い方だったけれど、今回は別の条件を優先した」といったケースもあり、決してあなた個人が否定されたわけではありません。それでも、何度も不採用が続くと「自分には価値がないのでは」と落ち込んでしまうこともありますよね。でも、アドバイザーに相談することで、どこを改善すればいいのか、どう伝え方を工夫すれば次につながるかなど、具体的なフィードバックを受けることができます。結果に一喜一憂するのではなく、「選考を通じて自分を磨く時間」ととらえることで、少しずつ前に進んでいくことができます。
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか口コミや体験談を調査しました
dodaチャレンジを利用しようとした方の中には、実際に求人を紹介してもらえなかった、あるいはサポートの利用を見送るよう提案されたという経験をされた方もいます。これは「dodaチャレンジが冷たい」「断られた=価値がない」といったことでは決してなく、あくまでその時点での就労状況や支援の必要性に応じた判断である場合がほとんどです。この記事では、実際に「断られてしまった」と感じた方たちのリアルな体験談を通して、どのような状況でサポート対象外と判断されるのか、またその背景にはどんな理由があるのかを探っていきます。それぞれのエピソードは辛さや戸惑いがあったかもしれませんが、同時に「今の自分に合った支援を考えるきっかけになった」という前向きな気づきにもつながっています。
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。紹介できる求人がないと言われてしまいました
この方の場合、障がい者手帳を所持しているにもかかわらず、「紹介できる求人がありません」と案内されてしまったことで、かなり落ち込んだといいます。理由としては、希望する働き方とスキル・経験との間にギャップがあったことが大きかったようです。特にデスクワーク系や在宅勤務の求人を希望していたものの、PC操作が苦手で実務経験も少なかったため、企業への紹介が難しいと判断されたそうです。「自分を否定されたようで辛かった」と振り返っていましたが、後に職業訓練を受けてスキルを身につけたことで、再チャレンジの道が開けたと語っていました。一度断られたとしても、それは「今の自分にとって無理のない選択肢かどうか」を見極める大切な判断であり、可能性を広げるためのステップにもなり得るのです。
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
「働きたい気持ちは強くあるのに、なぜ利用できないのか」と戸惑ったというこちらの体験談では、dodaチャレンジの面談後に「まずは就労移行支援を利用して、生活リズムを整えるところから始めましょう」と案内されたとのことです。体調の波が大きく、週5日勤務が難しい状態だったこともあり、いきなり一般就労に進むのはリスクが高いと判断されたようです。本人としては前向きに取り組む意志があっただけに、最初は「断られた」と感じたそうですが、振り返ってみると「自分の状態をきちんと見てくれていた」と思えるようになったと語っています。その後、就労移行支援事業所での訓練を経て、あらためてdodaチャレンジを利用し、スムーズに転職につなげられたとのことでした。焦らず、自分に合ったタイミングを見極めることの大切さが伝わる体験です。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。
dodaチャレンジに相談したものの、『ブランクが長く、就労経験が直近にないため、まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう』と提案されました
長年の療養生活を経て、ようやく働く意欲が戻ってきたというこちらのケースでは、「やっと社会復帰の一歩を踏み出そうとしたのに、また入口で止められた気がして正直つらかった」と話していました。とはいえ、アドバイザーからは無理に求人をすすめられることはなく、「今の生活リズムや健康状態を大切にしながら、少しずつ準備していきましょう」と丁寧に説明を受けたそうです。当初はショックもあったものの、「今の状態を否定されたわけではない」「今すぐでなくてもいい」と思えるようになったとのことでした。焦らず自分のペースで復帰を目指すために、段階的な支援を活用するという考え方が、長い目で見れば自分を守ることにつながるという気づきもあったようです。
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
地方在住の方の中には、「地元で働きたいけれど、やりたい仕事がなかなか見つからない」と悩む方も多いです。この方もそのひとりで、地元・四国の小さな町に住みながら、クリエイティブな仕事に挑戦したいという思いを持ってdodaチャレンジに登録されたそうです。希望は在宅でできるライターやデザイン職。しかし、実際にはそのような職種の求人が地方では少なく、加えて完全在宅が条件となると、さらに選択肢が狭まってしまいます。担当アドバイザーからは「現時点でご希望に沿う求人はご紹介が難しいです」と案内され、大きなショックを受けたと語っていました。それでも、話をする中で「まずはスキルを磨き、ポートフォリオを充実させる」「フリーランスの働き方も視野に入れる」といった新たな目標が見えたそうです。求人がない=キャリアの終わりではなく、準備の時間として捉えることも前向きな一歩になります。
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。dodaチャレンジに登録したら、『現時点では正社員求人の紹介は難しいです』と言われました
非正規雇用の経験しかない方にとって、「正社員として安定して働きたい」という思いはとても強いものですよね。この方も、過去にはアルバイトや短期の派遣の仕事を繰り返してきたものの、キャリアの軸が定まらず、自信も持てなくなっていたそうです。dodaチャレンジに登録し、「そろそろ正社員を目指したい」と伝えたところ、アドバイザーからは「今のご経験だけでは、正社員求人のご紹介は難しい」との言葉が返ってきたとのこと。一度は落ち込んだものの、「紹介できない理由」をしっかり説明してもらえたことで、次にやるべきことが見えてきたといいます。結果として、まずは長期派遣での就業を経て、職歴を積み直し、再度チャレンジする道を選ばれたそうです。「断られた」のではなく、「今はまだ準備が必要な段階」と捉え直すことで、前向きに気持ちを切り替えるきっかけになったと語っていました。
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
子育てと仕事を両立したいと考える方にとって、勤務条件はとても大切な要素です。この方は、子どもがまだ小さいため、通勤が難しく、週3回の短時間勤務で完全在宅、さらに年収もある程度を希望されていました。希望職種は事務系でしたが、そのすべての条件を満たす求人はなかなか見つからず、dodaチャレンジからは「現時点ではご紹介が難しい」と伝えられてしまいました。もちろん、条件を提示することは悪いことではありません。ただ、条件が細かくなるほど、該当する求人の数は少なくなり、時期や地域によってはゼロということもあります。この方は後に「優先順位を整理しよう」と考えるようになり、まずは在宅と短時間勤務を重視し、年収については長期的に調整していく方針に切り替えたそうです。すべてを満たす求人が難しくても、どこかを柔軟に見直すことで道が開けることもあります。
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
精神障がいを抱える方にとって、「社会復帰したい」「少しずつ働きたい」という気持ちはあっても、制度的なハードルが存在することもあります。この方はうつ病の診断を受けており、現在も治療を続けながら「そろそろ働く準備を始めたい」と思ってdodaチャレンジに登録を試みたそうです。しかし、障がい者手帳をまだ取得していなかったため、サービス利用は難しいと案内されました。dodaチャレンジの求人の多くは障がい者雇用枠であり、企業との契約上「手帳の所持」が必要条件となっているため、現状では紹介が難しいという判断になったとのことです。その後、主治医と相談し、手帳申請の準備を進めることになったそうです。「手帳がないから就職できない」と思い込まず、制度を活用して一歩ずつ前進することが、選択肢を広げるための第一歩になると語ってくれました。
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
身体的な負担を軽減するため、これまでの軽作業から在宅勤務に切り替えたいという思いは、多くの方が持つものです。この方もその一人で、体調の安定を考慮し、ITエンジニア職への転職を目指してdodaチャレンジに相談しました。未経験ではありましたが、「オンラインで勉強を始めている」「これから手に職をつけたい」という意欲があったそうです。しかし、実務未経験の状態でエンジニア職を希望した場合、企業側が即戦力を求める傾向が強く、紹介できる求人が限られてしまうのが現状です。dodaチャレンジのアドバイザーからも、「現時点で未経験可のエンジニア求人はほとんどなく、ご紹介が難しい」と案内されたとのことでした。最初は残念に思ったそうですが、その後は就労移行支援でITスキルを磨き、実績をつくることで、将来的な再チャレンジを目指しているそうです。
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
身体的な制約がある中で、無理のない働き方を模索するのはとても大切なことです。この方は、通勤が難しいという事情があり、フルタイム勤務も体力的に不安があったため、週数回の短時間勤務かつ在宅ワークを希望してdodaチャレンジに相談されました。しかし、実際に紹介できる求人は「週5日フルタイム勤務」が条件となっているものが多く、短時間で完全在宅という条件を満たすものは非常に限られているため、アドバイザーからは「現時点で該当する求人がありません」との案内があったそうです。気持ちとしては「少しでも働きたい」という前向きな想いがあっただけにショックは大きかったとのことでしたが、今後はリモート対応の多い業界や在宅型就労支援制度など、より柔軟な働き方を提案してくれる支援機関とも連携しながら、少しずつ進んでいくつもりだと語ってくれました。
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。dodaチャレンジでは『ご紹介可能な求人は現在ありません』と言われました
これまでのキャリアを活かして、障がい者雇用でも責任ある立場や高収入を目指したいという希望を持つ方も増えています。この方も、前職では中堅企業の一般職として十分な経験を積んでおり、次の職場では「役職付き」「年収600万円以上」といった条件を目指していました。しかし、障がい者雇用枠においては、一般雇用と比べて管理職や高収入のポジションがまだまだ少なく、求人自体が非常に限定的であるのが現実です。dodaチャレンジのアドバイザーからは、「現時点でその条件に見合う求人はご紹介できません」と説明を受けたとのことでした。はじめは「希望を否定されたようで悔しかった」と話していましたが、今はキャリアアップに向けて専門スキルを磨きつつ、将来的なチャンスに備える期間として前向きに捉えているそうです。段階を踏んで挑戦していく姿勢が、よりよい未来につながると感じた体験でした。
dodaチャレンジで断られたときの対処法について詳しく紹介します
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかったり、「今はご紹介が難しいです」と言われたとき、落ち込んでしまうのは当然のことです。でも、その状況が「終わり」ではなく、「これからの準備を始めるきっかけ」になることも多いんです。dodaチャレンジで断られる理由の多くは、一時的なスキル不足や就業経験の少なさ、希望条件とのミスマッチなどです。つまり、自分自身が努力できる部分や、外部のサポートを受けて改善できる部分もたくさんあるということ。ここでは、特にスキルや職歴の不足を理由に断られてしまった場合の対処法について、具体的な方法をご紹介します。小さな一歩の積み重ねが、数ヶ月後には大きな自信となって返ってくることもあります。焦らず、自分のペースでできることから始めてみましょう。
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
「これまでの仕事は軽作業や単発バイトばかりだった」「パソコンはタイピングぐらいしかできない」「職歴を聞かれるのが不安…」という方は、dodaチャレンジでも求人紹介が難しいと判断されることがあります。でも、だからといってチャンスがないわけではありません。スキルや経験は、これから身につけることができますし、サポートしてくれる制度もたくさんあります。ここでは、「今は経験が足りない」と言われた方が、次に何をすればいいのかを具体的にまとめました。
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
職歴やスキルに自信がない方におすすめなのが、ハローワークで紹介している職業訓練(公共職業訓練・求職者支援訓練)です。多くの自治体で開催されていて、WordやExcelの基本操作、ビジネスマナー、パソコンを使った事務処理など、就職に役立つ実践的なスキルを無料または非常に安価で学ぶことができます。中には障がいのある方向けのサポートが整ったコースもあり、安心して学べる環境が用意されています。修了後には修了証が発行されるため、履歴書にも書けて、応募書類のアピールにもつながります。「いきなり働くのは不安」「まずはスキルを身につけたい」という方には、まずこの職業訓練からスタートするのがとても効果的です。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
障がいのある方が働くための準備をする場として、「就労移行支援」という福祉サービスがあります。この制度では、パソコン操作や事務スキルの習得に加え、職場で必要とされる報連相や電話対応といったビジネスマナーの練習、さらに体調管理やストレス対処法など、就労に必要なさまざまな支援が受けられます。定期的な面談やメンタルサポートも含まれているため、体調に不安がある方やブランクがある方でも、安心して少しずつ就労への準備ができます。就労移行支援事業所を修了したあとに、あらためてdodaチャレンジに登録し、希望の求人を紹介してもらえるようになったという方も少なくありません。自分のペースで力をつけながら、「働ける自分」を目指せる場として、とても心強いサポートです。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
スキル不足で求人が見つからなかったという方にとって、資格取得はとても有効な手段です。特に事務職やデータ入力などを目指している場合、MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級といった資格は、求人票に「歓迎スキル」として書かれていることが多く、取得しておくだけで応募できる求人の幅が一気に広がります。勉強方法も、就労移行支援や職業訓練、または市販のテキストや通信講座を活用するなど、さまざまな選択肢があります。資格は履歴書にも書ける“目に見える成果”なので、「何を頑張ったら良いかわからない」という方にもぴったりです。いきなり就職を目指すのではなく、準備期間として資格取得をゴールにすることで、自信を持って再チャレンジしやすくなります。
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養期間があるなど)の対処法について
療養や体調面の問題で長い間働けなかったという方にとって、「もう一度働きたい」と思っても、その第一歩がとてもハードル高く感じられるものです。実際にdodaチャレンジの面談で、「ブランクが長くてすぐの就職は難しい」「まずは準備を優先しましょう」と案内されるケースも少なくありません。でも、これは決して拒否されているわけではなく、“段階的なステップを踏んでから就職活動を進めた方が長く安定して働ける”という配慮なのです。ここでは、ブランクが長い方が焦らずに一歩ずつ前に進むための具体的な対処法をご紹介します。無理なく働くための「助走期間」は、結果的に自信や実績にもつながり、次のステージへとつながっていく土台になります。
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
長いブランクがある方にとって、まず大切なのは「生活リズムを整えること」そして「働く準備を少しずつ取り戻すこと」です。就労移行支援は、そのための第一歩としてとても有効な制度です。ここでは、週に何日か通所しながら、ビジネスマナー、パソコンスキル、履歴書の書き方、模擬面接など、実際の職場で必要とされるスキルを練習できます。また、支援員がメンタル面のサポートも行ってくれるので、体調や気持ちの波がある方でも安心して取り組むことができます。毎日通う習慣ができることで、面接時にも「継続的に通所して訓練を続けています」と自信を持って伝えることができるようになります。実績を積みながら、少しずつ社会とのつながりを取り戻していく――そんな場として、就労移行支援はとても心強い味方になります。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
いきなりフルタイムでの勤務や正社員就職を目指すのではなく、まずは「自分にできる範囲で少しずつ働いてみる」ことから始めるのも立派な第一歩です。たとえば、週に1〜2回の短時間のバイトや、在宅でできる単発ワークなど、自分のペースで働ける仕事を通じて、“継続して仕事ができる”という実績を作っていくことが大切です。これは、次にdodaチャレンジなどの転職支援サービスを利用する際にも、「ブランクはあるけれど、少しずつ社会復帰しています」とアピールできるポイントになります。自信が持てない時期こそ、小さな成功体験を積むことが大きな支えになります。どんなに短時間でも、「働けた」という事実は、次のステップへの確かな土台になるのです。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
「まだ働く自信がないけれど、職場の雰囲気を体験してみたい」という方にぴったりなのが、企業での実習やトライアル雇用です。ハローワークや就労移行支援を通じて紹介されることが多く、一定期間、企業での就業体験ができる制度です。これは「お試し雇用」として位置付けられることもあり、企業側も採用の前段階として協力的に受け入れてくれることが多いです。実習を通して自分の得意・不得意を知ることができたり、職場でのコミュニケーションを再確認できる良い機会にもなります。また、このような実績があると、再びdodaチャレンジに相談した際にも「働ける土台がある方」として、アドバイザーの印象も良くなり、紹介できる求人の幅が広がることがあります。ブランクを取り戻す準備として、まずは現場に少し触れてみることも大切な一歩です。
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
地方に住んでいると、どうしても都市部と比べて求人の数や業種が限られてしまうという現実があります。特に障がい者雇用枠においては、全国対応のサービスを利用しても、地域によっては「ご紹介できる求人がありません」と言われてしまうこともあります。また、通勤が困難な方が「在宅勤務限定」「フルリモート希望」と条件を出すと、紹介可能な求人はさらに限られてしまうのが現状です。dodaチャレンジから断られてしまったとしても、選択肢は他にもあります。在宅でできる仕事を探したり、他の障がい者向けサービスを併用することで、自分に合った働き方が見つかる可能性は十分にあります。ここでは、地方在住の方が次の一歩を踏み出すために取れる具体的な対処法をご紹介します。
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
dodaチャレンジでは在宅勤務可能な求人も扱っていますが、フルリモートかつ地方在住の方に合う求人は非常に少ないのが実情です。そこでおすすめなのが、他の障がい者向け就職支援サービスを併用することです。たとえば「atGP在宅ワーク」では、在宅勤務に特化した求人を多く取り扱っており、通勤が困難な方でも応募できる仕事に出会える可能性があります。また、「サーナ」や「ミラトレ」など、障がい特性やライフスタイルに寄り添ったサポートを行っているサービスもあります。1つのエージェントだけに頼るのではなく、複数の窓口を持つことで、自分に合った仕事やサポートに出会いやすくなります。登録や相談は無料なので、まずは情報収集からでも始めてみるのがおすすめです。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
「どうしても在宅勤務がしたいけれど、紹介してもらえる求人がない」という場合には、クラウドソーシングサービスを使って、自分で仕事を受けてみるのも一つの方法です。ランサーズやクラウドワークスなどでは、ライティング、データ入力、画像加工、商品登録といった未経験でも取り組める仕事が多数掲載されています。短期・単発の案件も多いため、自分のペースで仕事を始めやすいのが特長です。こうした仕事を継続することで、「在宅でも働ける」「納期を守って業務をこなせる」といった実績になりますし、将来的にdodaチャレンジや他のエージェントに再登録する際のアピール材料にもなります。最初は小さな案件からで構いません。自分で選んだ仕事をやり遂げたという経験が、自信にもつながります。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
地方に住んでいる場合、求人情報をインターネットや全国規模のサービスだけに頼っていると、地元の求人に出会えないことがあります。そこで活用したいのが、地域に根ざした支援機関です。障がい者就労支援センターや福祉型ハローワーク(就労支援専門窓口)では、地域の中小企業や事業所とのつながりがあり、地元ならではの求人情報を紹介してもらえることがあります。さらに、通勤の相談や職場見学、職場実習などもサポートしてくれることが多く、「知らなかった選択肢」に出会えることも。ネットでは見つからなかった求人や、柔軟な働き方をしてくれる企業に出会えるチャンスも広がります。まずは一度、最寄りの支援センターに足を運んでみることをおすすめします。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
働き方に対する希望がはっきりしているのはとても良いことですが、条件が細かすぎたり理想が高すぎると、どうしても求人紹介が難しくなってしまう場合があります。たとえば「完全在宅で週3日、しかも年収は300万円以上」といった条件をすべて満たす求人は、障がい者雇用枠ではかなり限られているのが現実です。dodaチャレンジでも、希望条件が多すぎると「現時点ではご紹介できる求人がありません」と言われてしまうことがあります。そんなときに大切なのは、「自分にとって何が一番大事なのか」を整理して、アドバイザーと一緒に優先順位を再検討することです。すべてを一気にかなえるのではなく、まずはどこか一つを叶えてスタートする、という視点も持つと、現実的な選択肢が広がっていきます。
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
まず取り組みたいのは、自分の希望条件に優先順位をつけることです。理想の働き方をイメージするのはとても大切ですが、すべての条件を一度に満たす求人はどうしても限られてしまいます。そのため、「これは絶対に譲れない」という条件と、「できればこうだったら嬉しい」と思う条件を明確に分けてみましょう。たとえば「通勤が体力的にきついので在宅勤務は必須」なのか、それとも「時短勤務が理想だけど、体調次第ではフルタイムも考えられる」のかなど、現実と気持ちをすり合わせながら整理していくことが大切です。優先順位を決めておくことで、アドバイザーも求人提案がしやすくなり、マッチングの幅が広がります。柔軟な姿勢が、新しい可能性につながっていきます。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
条件の見直しは、アドバイザーとの連携がとても重要です。最初に伝えた条件が原因で求人紹介を断られてしまった場合も、「この部分なら少し緩めても大丈夫」といった譲歩ポイントが見えてきたら、再度アドバイザーに伝えてみましょう。たとえば「週5日は難しいと思っていたけど、週4勤務なら可能」「完全在宅希望だったけど、週1の出社ならできるかも」など、小さな調整が求人のマッチングにつながることもあります。勤務地についても、自宅から通える範囲を少し広げてみるだけで、見つかる求人が増えることもあります。条件をゆるめることは「妥協」ではなく、「現実に合った柔軟な戦略」と捉えることで、より現実的な転職活動が進めやすくなります。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
最初からすべて理想どおりの働き方を目指すのではなく、「まずは土台をつくって、徐々にキャリアアップしていく」という戦略を持つことも大切です。たとえば「今は在宅勤務じゃないけど、職場に慣れてから在宅に切り替えられる会社を選ぶ」「最初は年収が低めでも、スキルを積んで1〜2年後に昇給を目指す」といった段階的なゴール設定をすることで、焦らず自分のペースで理想に近づくことができます。アドバイザーと相談しながらキャリアパスを描くことで、「今できること」と「将来目指すこと」のバランスがとれた転職活動になります。理想に届く道は一つだけではありません。少しずつ経験を積み重ねていくことで、結果的に自分にとって無理のない働き方に近づいていけるのです。
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
dodaチャレンジの求人は、多くが「障がい者雇用枠」での募集となっているため、基本的に障がい者手帳の所持が必須とされています。そのため、まだ手帳を取得していない方や、申請中・取得予定が未定という方は、「求人の紹介ができません」と案内されることがあります。特に精神障がいや発達障がいの場合は、手帳取得までの流れや期間が不透明になりやすく、不安を抱えてしまう方も少なくありません。でも、焦らなくて大丈夫です。状況に応じた支援や、今できる行動はたくさんあります。ここでは、手帳がまだ取得できていない場合や、区分の関係でサポート対象外になってしまったときの対処法を3つご紹介します。いずれも「いまは難しくても、ゆくゆくは働きたい」という思いを前提に、次の一歩につながる道です。
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
「障がい者手帳がない」と一言で言っても、「申請をしていない」「どうやって申請すればいいか分からない」「そもそも対象になるか分からない」と悩みの理由は人それぞれです。精神障がいや発達障がいであっても、一定の条件を満たせば手帳の取得は可能です。まずは、かかりつけの主治医に相談し、診断書の発行について話をしてみましょう。その上で、自治体の障がい福祉窓口で申請手続きを行う流れになります。取得には時間がかかる場合もあるため、早めに動き出すことが大切です。「手帳があれば使える支援の幅が広がる」ということを知っておくだけでも、行動の後押しになります。分からないことがあれば、自治体の障がい福祉担当者や福祉事務所に相談してみるのがおすすめです。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
手帳がまだ取得できていないからといって、働くことを完全にあきらめる必要はありません。ハローワークでは、障がい者手帳を持っていない方でも応募可能な「一般枠」の求人や、配慮のある職場を紹介してもらえることがあります。また、就労移行支援の中にも「手帳の有無を問わず通える事業所」も存在しており、まずはここでスキルを身につけてから、dodaチャレンジのような支援サービスに再チャレンジするという選択もあります。一度「お断り」と言われても、それは今このタイミングでの話。就労移行支援を利用して働く準備を整えたり、職歴やスキルの実績を積んだ上で、数ヶ月後に再びdodaチャレンジに相談した方がスムーズに進められたというケースも多いです。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
障がい者手帳の取得には、医師の診断書が必要となるため、「今は手帳のことを考えるよりも治療に集中した方がいい」と言われる場合もあります。実際、体調がまだ安定していない状態で就職活動を無理に進めてしまうと、就職後に働き続けることが難しくなってしまうこともあります。もしdodaチャレンジから「現時点ではサポートが難しい」と案内された場合でも、それは否定ではなく「今は少し準備期間に充てましょう」というアドバイスであることがほとんどです。主治医と相談しながら、まずは生活リズムや体調の安定を優先し、手帳が取得できた段階であらためて登録・相談する流れを考えてみましょう。焦らなくても大丈夫。今のあなたに合ったステップで、少しずつ前に進めばいいんです。
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
dodaチャレンジで「求人を紹介できません」と言われたとき、落ち込んでしまうのは無理もありません。でも、転職支援サービスはdodaチャレンジだけではありませんし、他のサービスを併用することで、自分に合う選択肢が見つかることも多いです。たとえば、障がい者向けに特化した転職エージェントである「atGP」は、在宅勤務やフレックス制度のある求人に強みがあり、特に在宅希望の方からの支持が高いです。ほかにも「ラルゴ高田馬場」「ミラトレ」「クローバーナビ」「ウェルビー」など、就労移行支援を提供しつつ、企業とのマッチングに力を入れている事業所もあります。
また、地域に根ざした支援を重視したい場合は、お住まいの地域の就労支援センターや、ハローワークの「専門援助部門」を活用するのもおすすめです。自治体ごとに連携している事業所や企業とのつながりがあるため、地元での就職を希望する場合にも有効です。
転職活動を進めるうえで大切なのは、「一つのサービスでうまくいかなかったから終わり」と思わずに、自分にとって無理のない方法を見つけていくことです。複数のサービスを比較・併用しながら、信頼できる支援者や環境に出会うことで、自然と前向きな気持ちも生まれてきます。焦らず、今できることから一歩ずつ進めていくことが、何よりも大切です。
dodaチャレンジで断られた!?精神障害や発達障害だと紹介は難しいのかについて解説します
「dodaチャレンジに登録しようとしたけれど、精神障害や発達障害が理由でサポートを受けられなかった…?」そんな不安を感じている方も少なくないかもしれません。結論からいえば、精神障害や発達障害だからといって一律に「紹介不可」となることはありません。ただし、就労に対する準備状況や生活の安定度、手帳の有無、支援内容のすり合わせによっては、一時的に求人の紹介が難しくなるケースがあるのも事実です。特に精神疾患や発達障がいは、体調の波や職場でのコミュニケーションなど、環境による影響が大きいため、サポート側としても慎重に判断することがあります。ここでは、精神障害や発達障害の方がdodaチャレンジを活用するうえでの注意点や、実際の支援体制の違いについて解説していきます。
身体障害者手帳の人の就職事情について
身体障害者手帳を所持している方にとって、就職活動の際に求められる配慮は比較的明確で、企業側としても受け入れ体制を整えやすい傾向があります。たとえば、視覚や聴覚、肢体不自由など、障がいの内容が物理的に見えやすく、かつ配慮が具体的である場合、「職場の構造を変える」「PC環境を整える」「会議のスタイルを工夫する」といった対応がしやすくなります。その結果、企業にとっても受け入れやすい存在となり、dodaチャレンジでも比較的スムーズに求人紹介につながることが多いです。ただし、すべての身体障がいの方が就職しやすいというわけではなく、職場環境や業務内容とのマッチング次第で難易度は異なります。
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
身体障害者手帳の等級が比較的軽度な方の場合、企業側としても「業務に支障が出にくい」「必要な配慮が最小限で済む」といった理由から、前向きに採用を検討されやすい傾向があります。たとえば、通勤が可能であり、業務中の特別な支援が不要であれば、通常のオフィスワークと大きな差がないと判断されることも少なくありません。また、軽度の障がいであることで、求人の選択肢も広がるという利点があります。ただし、等級が低い=配慮が不要というわけではなく、「本人にとって無理のない働き方をどう実現できるか」が常に大切な視点となります。採用後の職場定着のためにも、軽度だからこそ起こりうる「見えづらい困難」についても事前に相談し、丁寧にすり合わせていくことがポイントです。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
身体障がいは外見や動作の制限などが比較的分かりやすいため、企業側が必要な配慮をイメージしやすく、「どのようにサポートすればよいか」が明確な分、採用のハードルが下がる傾向があります。たとえば、車いすの利用者であればバリアフリーの設備が整っている職場を選ぶ、聴覚に障がいがある方には筆談やチャットを活用するなど、具体的な対応策を事前に準備しやすいのです。dodaチャレンジでも、こうした背景から身体障がいのある方への求人紹介は比較的スムーズに進むことが多く、職場とのマッチング精度も高くなる傾向があります。ただし、障がいの程度や環境との相性も大きく影響するため、「見えやすい=簡単」という認識ではなく、丁寧なコミュニケーションを通じて最適な働き方を探ることが大切です。
企業側が合理的配慮が明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
身体障がいの場合、必要とされる配慮内容が比較的明確で、企業側としても「何を準備すれば良いのか」が判断しやすいため、採用に前向きな傾向があります。たとえば、車いすを利用している方であれば、オフィスのバリアフリー化やトイレの整備、エレベーターの有無といった環境整備が検討対象になりますし、業務内容についても「重い物を持たないようにする」「長時間の立ち仕事を避ける」といった対応が取りやすくなります。こうした合理的配慮が具体的で準備しやすいことで、企業も安心して受け入れを進められるのです。dodaチャレンジなどのエージェントを通じて、事前に配慮内容をすり合わせることで、企業側も不安なく採用に踏み切ることができるのも、大きなメリットのひとつです。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
一方で、上肢や下肢に障がいがあり、移動や通勤に制限がある場合は、対応可能な求人が限られてしまうケースもあります。たとえば、「自宅から公共交通機関での通勤が困難」「階段の昇降が難しい」「長時間の作業姿勢が保てない」といった制約があると、業務環境や職場へのアクセスが採用の可否に影響することがあります。また、在宅勤務に対応していない企業では、リモート勤務が難しく、通勤必須の職場だとマッチングしにくくなってしまいます。そのため、事前に通勤可能な距離や環境、業務上の制約を丁寧に整理しておくことが重要です。dodaチャレンジのようなエージェントを通して企業に具体的な状況を伝えることで、配慮が得られるケースもありますので、自分の希望と制約をしっかり伝える準備が大切です。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
身体障がいがあっても、業務に支障のない範囲での会話や報連相がスムーズに行える場合、企業はその方を「一般的な職種」にも問題なく適応できると判断しやすくなります。たとえば、事務職やカスタマーサポート、営業事務など、コミュニケーション能力が求められる仕事でも、身体的な障がいが業務に直接支障をきたさないと判断されれば、障がいの有無に関係なく採用される可能性があります。dodaチャレンジでも、こうした「職務遂行能力に影響が出にくい」ケースでは、選考が比較的スムーズに進むことが多いです。コミュニケーションに不安がない方は、職種の幅を狭めずに求人に挑戦してみることで、思わぬチャンスが広がることもあります。
PC業務・事務職は特に求人が多い
身体障がい者向けの求人の中でも、特に多いのがPCを使用する事務職やバックオフィス業務です。これらの職種は、体を動かす業務が少なく、座ったままでも十分に作業ができるため、身体的な制約がある方にも適しています。業務内容も、データ入力、資料作成、請求処理、メール対応などが中心となるため、経験がなくても基本的なPCスキルがあれば応募可能な求人が多く見つかります。また、企業側も在宅勤務や時短勤務などの柔軟な働き方を導入しやすい職種であるため、身体的な負担が少ない働き方を希望する方にとっては非常に相性の良い分野です。dodaチャレンジでも、こうした事務系求人は紹介件数が多く、未経験OKの案件も豊富なので、まずはこの分野からスタートしてみるのもおすすめです。
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について
精神障害者保健福祉手帳を所持している方にとって、就職活動にはいくつか特有の難しさがあります。特にdodaチャレンジのようなエージェントでも、精神障がいのある方にはより丁寧なヒアリングとマッチングが行われます。それは、見た目では分かりにくい障がいであるからこそ、企業側が配慮すべきポイントをしっかり理解していないと、職場でのミスマッチや早期離職につながってしまう可能性があるからです。とはいえ、精神障害があるからといって就職が難しいわけではありません。大切なのは、自分の体調や特性をしっかり把握し、必要な配慮を言語化できるかどうか。そして「どんな働き方なら自分らしく働けるのか」を明確にすることが、企業との信頼関係を築く第一歩になります。
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
精神障がいをお持ちの方が就職活動をするうえで、企業側が最も重視するのは「継続して働けるかどうか」です。もちろん、誰にとっても体調に波はありますが、精神障がいの場合は特にストレスや環境の変化に敏感であることが多く、企業としても「長く働き続けてもらえるか」「急な休職が必要になるのではないか」といった不安を持ちやすい傾向にあります。そのため、症状の安定性や、日常生活や仕事への影響がどの程度かを整理して伝えることがとても大切です。「週5日通勤が可能」「決まった時間に働ける」「サポートがあれば対応できる作業範囲が広がる」など、自分が働くうえでの強みや工夫を具体的に伝えることで、安心してもらえるケースが増えてきます。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障がいや発達障がいのような“見えにくい障がい”は、採用する側からすると「具体的に何を配慮したら良いのかが分からない」という不安を抱きやすいのが現実です。たとえば、身体障がいであれば設備や業務の調整などが比較的分かりやすく準備できますが、精神障がいの場合は「急に体調が悪くなったら?」「どんな声かけが適切か?」といった対応がケースバイケースであることから、企業が戸惑うこともあります。だからこそ、自分自身が「こんなときに体調を崩しやすい」「こういうサインが出たら休憩が必要」など、自分の特性を冷静に伝えられるかどうかがカギになります。自分を守るためにも、企業との信頼を築くためにも、あらかじめ丁寧に共有する姿勢が大切です。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
精神障がいのある方が採用面接を受ける際、どのように配慮を伝えるかはとても重要なポイントです。とはいえ、「すべてを包み隠さず話さなければいけない」というわけではありません。大切なのは、業務に関係する部分を中心に「どんな配慮があると働きやすいか」「どういったことに困りやすいか」を具体的に伝えることです。たとえば「緊張すると言葉が詰まることがあるので、少しだけ考える時間をいただけると助かります」「体調を維持するために週に一度の通院が必要です」など、実際の仕事に影響する部分を共有することで、企業側も「どう対応すれば良いか」が見えやすくなります。dodaチャレンジでは、このような伝え方のサポートも行ってくれるので、面接前にアドバイザーと相談して準備するのがおすすめです。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
療育手帳(知的障害者手帳)をお持ちの方が就職活動を進める場合、そのサポート内容や就職先の選択肢は、手帳に記載されている区分(判定)によって大きく変わってきます。dodaチャレンジでも、知的障がいのある方からの相談を受けることはありますが、判断の軸となるのは「職場での理解が得られるか」「業務を継続できるか」といった観点です。知的障がいの場合、抽象的な指示や臨機応変な対応が難しい場面が出てくるため、業務内容が明確でマニュアル化されている職場との相性が良いとされています。一方で、本人の特性や得意な作業に合わせた仕事を見つけることができれば、一般就労での活躍も十分に可能です。就職活動を始める前に、まずは自分の区分や特性を整理し、どのようなサポートがあれば安定して働けるかを確認しておくことが大切です。
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
療育手帳には「A判定(重度)」と「B判定(中軽度)」という区分があり、この判定によって受けられる支援内容や就労の選択肢が異なります。A判定の方は、日常生活やコミュニケーションに支援が必要とされるケースが多く、就労にあたっても一定のサポート体制が必要となるため、まずは福祉的就労からスタートする方が多いです。一方で、B判定の方はある程度の自立生活が可能で、支援付きでの一般就労を目指すケースも増えています。この区分は一つの目安に過ぎませんが、企業や支援機関との連携を考える上での重要な情報になります。まずは自分の区分とできること・苦手なことを整理し、それに合った就労環境を探すことが、無理のないスタートにつながります。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
A判定(重度)の療育手帳をお持ちの方の場合、日常生活でも支援を必要とする場面が多いため、いきなり一般就労にチャレンジするのはハードルが高くなることがあります。そのため、多くの方が最初に利用するのが「就労継続支援B型」などの福祉的就労サービスです。ここでは、働く体力や集中力を身につけるための訓練や、簡単な作業を通じて「働く感覚」に慣れていくことができます。また、支援員が常にそばにいてサポートしてくれるため、安心して作業に取り組める環境が整っています。もちろん、B型からA型や一般就労へとステップアップしていく方も少なくありません。焦らずに自分のペースで経験を積むことで、働く力をじっくり育てていくことができます。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
B判定(中軽度)の方の場合、日常生活はほぼ自立しており、軽度の支援で業務をこなせるケースも多く見られます。そのため、就労移行支援を経て一般就労を目指す方が増えているのも事実です。職場でのサポート体制が整っていれば、事務補助や軽作業、製造業務など幅広い職種での活躍が期待できます。また、集中力や丁寧な作業が得意な方は、データ入力や検品などの業務でも評価されやすいです。大切なのは、自分の得意・不得意を理解し、それを企業としっかり共有すること。dodaチャレンジでも、B判定の方が求人を紹介され、定着している事例は多数あります。自信が持てないときも、支援機関やアドバイザーと一緒に準備を進めていけば、少しずつ道が見えてくるはずです。
障害の種類と就職難易度について
障がいのある方の就職は、障害の種類によって難易度やサポートのあり方が大きく変わります。たとえば、身体障がいの方は配慮内容が明確で企業側も対応しやすいため、比較的就職しやすい傾向があります。一方で、精神障がいや発達障がい、知的障がいの方は「見えにくい障がい」であるため、働く環境との相性やコミュニケーションのすり合わせが重要になります。どの障害も「就職が無理」ということは決してありませんが、自分の特性を正しく理解し、それに合った職場選びとサポート体制を整えることが何より大切です。dodaチャレンジをはじめ、専門エージェントや支援機関の協力を得ながら、焦らず一歩ずつ前に進んでいくことが、長く働き続けるための近道になります。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
就職活動を考える際に、「障害者雇用枠で応募するか」「一般雇用枠でチャレンジするか」で迷う方も少なくありません。どちらの雇用形態にもそれぞれの特徴があり、本人の体調や希望する働き方、企業側のサポート体制との相性によって向き不向きがあります。障害者雇用枠は、障がいがあることをオープンにして配慮を受けながら働くことを前提とした枠です。一方、一般雇用枠は障がいの有無を問わず、すべての応募者が同じ条件下で選考を受けるものです。どちらが「正解」というわけではなく、自分にとって無理のない働き方ができる選択肢を見極めることが何より大切です。ここでは、それぞれの特徴について詳しく見ていきます。
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠は、国の法律に基づいて企業が設けている正式な雇用枠です。これは企業の「好意」や「特別な配慮」ではなく、法律によって定められている雇用義務の一環であり、企業には障がいのある方を一定の割合で雇用する責任があります。このため、障害者雇用枠で採用された場合、配慮を受けることが「特別扱い」と見なされることはありません。むしろ、法的な整備に基づいて整った環境で働けるため、安心して業務に集中できるというメリットがあります。求人も年々増加傾向にあり、配慮の具体性が求められる分、働きやすさや定着率の高さにもつながっています。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
障害者雇用枠が設けられている背景には、障害者雇用促進法という法律があります。この法律では、一定規模以上の民間企業は、全従業員のうち2.5%以上(2024年4月からの新基準)を障がい者として雇用しなければならないと定められています。企業がこの法定雇用率を満たせない場合、納付金制度に基づくペナルティが発生するため、実際には多くの企業が障がい者の採用に積極的です。このような背景から、障害者雇用枠での採用は、企業・求職者の双方にとって「制度として保障された仕組み」となっており、安定した就労がしやすい枠でもあります。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
障害者雇用枠では、応募の段階から「障がいがあることを開示する(オープン就労)」ことが前提となります。そのうえで、どのような配慮が必要か、どんな場面で困りやすいかなどを明確に伝えることが、企業とのマッチング成功のカギになります。「配慮してもらうこと=甘え」ではなく、自分が安定して働くための必要なサポートとして、事前にすり合わせることができるのがこの枠の大きな利点です。実際に、dodaチャレンジなどでは、配慮事項の整理や面接時の伝え方についてもサポートしてくれるため、「どう伝えていいか分からない」と不安を感じている方でも安心して準備を進めることができます。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠は、いわゆる「通常の求人枠」であり、障がいの有無に関係なく、すべての応募者が同じ基準で選考を受ける枠です。この枠では、障がいのことを開示せずに応募する「クローズ就労」も可能ですが、採用後に配慮を受けにくい、または制度的な支援がないといった側面もあります。とはいえ、「自分で体調をコントロールできる」「配慮が特に必要ない」という方にとっては、より幅広い職種や待遇の求人にチャレンジできる機会でもあります。ただし、採用後に何らかの事情で支援が必要になった場合、社内の理解が得られにくいこともあるため、応募前によく考え、必要に応じて相談できる体制を整えておくことが大切です。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
一般雇用枠では、障がいのある方が「障がいを企業に開示するかどうか」を自分で選べるという大きな特徴があります。これを「オープン就労」「クローズ就労」と呼びます。オープン就労とは、応募時や面接で障がいの内容を伝えたうえで働く方法です。配慮を求める代わりに、仕事内容や働き方のすり合わせがしやすくなります。一方でクローズ就労は、障がいを開示せずに一般の応募者と同じ条件で選考に臨む方法です。特に軽度の障がいで業務に支障が出にくい方は、クローズで応募することで、より多くの求人にチャレンジできるというメリットがあります。ただし、職場で困ったときに配慮が得られにくい場合もあるため、自分の障がいや体調との向き合い方をふまえて、どちらの働き方が自分に合っているかを慎重に選ぶ必要があります。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠では、企業は障がいの有無を問わず、応募者全員に対して平等な条件で選考を行います。そのため、障がい者雇用枠と異なり、基本的に配慮や特別なサポートは制度として用意されていないのが前提です。たとえば、体調に合わせた勤務時間の調整や、作業内容の一部変更、通院配慮などは、こちらから具体的に交渉しない限り自動的に提供されることはありません。そのため、クローズ就労を選ぶ場合は、「困ったときにどうするか」「必要な配慮を誰にどう相談するか」といった準備を事前にしておくことが重要になります。反対に、そうした配慮が必要ない、あるいは自分でコントロールできるという方には、待遇面やキャリアの選択肢が広がるという大きなメリットもあります。どちらを選ぶかは、自分の状況と価値観に合った形をじっくり考えることが大切です。
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障がい者雇用において、「年齢によって採用されやすさが変わるのでは?」という不安を持つ方は少なくありません。実際に、障害者雇用状況報告(令和5年・2023年版)をもとに見ると、年代ごとの雇用状況には一定の傾向が見られます。たとえば、20代〜30代の若年層は、社会経験が浅い分、ポテンシャル採用や長期育成を前提とした求人が多く、未経験でも応募できるチャンスが比較的多いです。一方で、40代以降になると、経験や即戦力が求められる求人が増えるため、「職務経歴」や「スキルの有無」が大きな判断材料になる傾向があります。とはいえ、年齢だけで不利になるというよりは、「年齢×これまでの経験×働きたい意思」のバランスをどう伝えるかが鍵になります。年齢が高くても、スキルや安定した就労歴がある方は高く評価されるケースも多く、採用されている実例はたくさんあります。
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
厚生労働省が毎年公表している「障害者雇用状況報告」によると、2023年の時点で障がい者雇用数は増加傾向にあり、特に精神障がい者の就労件数が年々伸びています。年代別に見ると、20代の雇用割合が最も多く、次いで30代、40代と続きます。これは若年層に対する採用意欲の高さや、社会全体として「若いうちから職場に慣れてほしい」という期待があることを反映していると考えられます。しかし40代・50代以上でも、業務経験が豊富だったり、落ち着いて仕事に取り組める安定性が評価されて採用に至るケースは多数あります。また、年齢に関わらず「職場定着率」が高い人材を求める企業が増えているため、自分の年齢に自信が持てない方も、まずは自分の強みや働く意欲を伝える準備をしておくと良い結果につながる可能性があります。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い
20〜30代の若年層は、障害者雇用においても非常にニーズが高い年代です。実際に、厚生労働省の障害者雇用状況報告でも、20代・30代の採用数が最も多く、企業からの求人も比較的豊富に存在しています。若いということは、企業側からすると「長く育てられる」「柔軟に仕事を覚えてくれる」というポテンシャルが高く評価される要素になります。また、未経験OKの求人や、就業経験が少なくても応募可能なポジションも多いため、初めての就職や転職を目指す障がいのある方にとっては非常に追い風の年代です。特にdodaチャレンジなどのエージェントを活用すると、将来的なキャリアアップを見据えた求人や、成長を前提とした長期的なサポートが受けられるのも大きなメリットです。若いうちに職場経験を積んでおくことが、将来の選択肢を広げる大きな鍵にもなります。
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる
40代を過ぎると、障害者雇用でも求人の傾向が変わってきます。企業側は、年齢が上がるにつれて「即戦力」としてのスキルや経験を重視する傾向が強くなるため、20〜30代のように「未経験でもOK」といった求人は少なくなります。そのため、これまでの職務経歴にブランクがあったり、明確なスキルや実績がない場合には、マッチする求人が限られてしまうことがあります。ただし、逆に言えば、これまでのキャリアや専門知識を活かせる人材であれば、年齢に関係なく評価されるケースも少なくありません。たとえば、事務系・経理・管理部門・技術職など、特定の分野で経験を積んできた方は、それを活かした求人を狙うことで採用の可能性が高まります。スキルが不足している場合でも、職業訓練や就労移行支援を活用することで、再スタートを切ることは十分に可能です。
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い
50代以上になると、障害者雇用においてはさらに求人の幅が狭まりやすくなります。この年代では、企業側が「長期雇用」よりも「即戦力」や「短期的な業務補助」を期待することが多いため、募集されている仕事も「軽作業」「清掃」「事務補助」など、比較的業務が限定される傾向があります。また、体力や健康面への配慮も必要とされる年代でもあるため、フルタイム勤務ではなく、「週20時間未満の短時間勤務」や「通院に配慮できるシフト勤務」などを条件にした求人が増えてくるのも特徴です。ただし、これまでの経験や勤務態度が評価され、契約社員や嘱託職員として活躍しているケースもあります。大切なのは、自分にとって無理のない働き方を選び、その中で「どのように貢献できるか」を企業に伝えることです。年齢にとらわれず、前向きに自分の強みを伝える工夫が採用への近道になります。
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
障がい者向けの就活エージェントを利用しようと考えたとき、「年齢が高いと使えないのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、dodaチャレンジをはじめとする多くの障がい者専門エージェントでは、公式には年齢制限を設けていません。つまり、何歳であっても登録は可能です。ただし、実際のサポート対象や紹介される求人の傾向を見ると、エージェントが最も力を入れているのは20〜50代前半の層であることが多いです。これは、企業側が「長期就労」や「育成」を見込める年代に対して採用意欲を持ちやすいためであり、50代後半以降になると、どうしてもマッチングする求人が少なくなる傾向があります。年齢に不安がある場合は、複数の支援機関を併用することで、自分に合ったサポートを受けやすくなります。
年齢制限はないが 実質的には「50代前半まで」がメインターゲット層
dodaチャレンジでは公式には年齢制限を設けていませんが、求人紹介の中心となるのは20〜50代前半の方が多いのが実情です。特に企業側が想定している障がい者雇用のターゲット層は、比較的若く、今後も長期的に働いてもらえる可能性がある年代に集中しています。50代後半以降の方になると、「正社員での長期雇用」という枠にはなかなか当てはまりにくく、短時間勤務や契約社員としての雇用が中心となることが多くなります。ただし、これまでの職歴やスキルによっては、年齢に関係なく評価されるケースもあるため、自分の強みをしっかりと伝えられるように準備しておくことが重要です。また、「働き方の柔軟性」や「体調とのバランス」を重視した求人に焦点をあてて探すことも、年齢に応じた転職活動を成功させるコツとなります。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
年齢が高くなるにつれて、民間の転職エージェントだけでの就職活動に限界を感じることもあるかもしれません。そんなときは、地域のハローワークにある「障がい者専門窓口」や、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営する「障がい者職業センター」などの公的機関を併用するのが効果的です。これらの機関では、年齢や障がいの特性に応じたキャリアカウンセリング、職業評価、就職後の職場適応支援まで、幅広くサポートしてもらえます。また、地元企業とのつながりがあるため、地域密着型の求人に出会える可能性も高まります。民間と公的機関のサポートをうまく組み合わせることで、自分に合った働き方や就職のチャンスを広げることができます。ひとつの窓口にこだわらず、柔軟に相談先を増やしていくことが、年齢に関係なく前向きに就職活動を進めるポイントになります。
dodaチャレンジで断られたときの対処法についてよくある質問
dodaチャレンジに登録したけれど、「求人を紹介できないと言われた」「面談後に音沙汰がない」「希望条件が合わなかった」といった理由で前に進めず、不安や戸惑いを感じた方も多いのではないでしょうか。せっかく勇気を出して相談したのに断られてしまうと、「自分はもう就職できないのでは」と落ち込んでしまうこともあるかもしれません。でも、断られたからといって道が閉ざされるわけではありません。むしろ、その時点では条件や準備が少しだけ整っていなかっただけ、というケースがほとんどです。ここでは、実際に多くの方がつまずきやすいポイントや、断られた後にできる具体的な対処法について、よくある質問形式でわかりやすく解説していきます。再チャレンジのタイミングや、他の支援機関との併用方法など、前向きに次のステップへ進むヒントを見つけていただけたらうれしいです。
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジの口コミには、「配慮をしっかり聞いてくれる」「自分のスキルに合った求人を紹介してもらえた」といった前向きな声が多く見られます。一方で、「担当者との相性に差がある」「希望条件に合う求人がなかった」という意見もあり、評価は人によって異なります。サポート内容や対応スピードなどに関しても、利用者の感じ方に幅があるため、まずは実際に面談を受けてみて自分に合うかを確認してみるのがおすすめです。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
求人紹介を断られた場合は、自分の希望条件や現在のスキル、就労状況を見直してみることが大切です。希望が厳しすぎる場合は優先順位を整理し、譲れる条件を見つけて再提示することでチャンスが広がることもあります。また、他の就労支援サービスや、ハローワーク・就労移行支援などを併用してみるのも有効です。焦らずに準備を重ね、条件が整ったタイミングで再登録するという選択肢もあります。
関連ページ:dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
面談後に連絡がないと不安になる方も多いですが、その理由はさまざまです。たとえば、マッチする求人が一時的に見つかっていない場合や、担当者が複数の案件を並行して確認している途中ということもあります。また、連絡先の記載ミスやメールの受信設定が原因になっていることもあるため、一度自分から連絡を入れてみるのもおすすめです。それでも音沙汰がない場合は、他のエージェントを検討してみるのもひとつの手です。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡なしの理由と対処法/面談・求人・内定それぞれのケースと連絡なしの理由
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談は、転職エージェントとしての基本的なヒアリングに加え、障がいに関する配慮や働き方の希望など、個別の事情を丁寧に聞いてくれる点が特徴です。面談はオンラインまたは電話で行われ、事前に予約した日時に担当のキャリアアドバイザーと1対1で話を進めていきます。初めての方には少し緊張するかもしれませんが、無理に話す必要はなく、自分の言葉で今の状況を伝えることが大切です。面談でよく聞かれるのは、「どんな働き方を希望していますか?」「障がいの内容や体調について教えてください」「過去にどんな仕事をしてきましたか?」といった内容です。配慮事項についても「こういう環境だと働きやすい」など、なるべく具体的に伝えることで、求人紹介の精度がぐっと上がります。
関連ページ:dodaチャレンジの面談から内定までの流れは?面談までの準備や注意点・対策について
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がいのある方専門の転職・就職支援サービスです。一般的な転職エージェントとは異なり、障がい特性や配慮が必要なポイントを理解したキャリアアドバイザーが担当してくれるのが大きな特徴です。サービスの内容としては、登録後にキャリア面談を行い、その後、希望条件に合う求人を紹介してくれる流れです。求人の種類も、事務職やIT職などのオフィスワークから、在宅勤務、時短勤務のような柔軟な働き方まで幅広く扱っています。また、履歴書や職務経歴書の作成サポート、面接対策、企業との条件交渉まで、就職に必要なサポートが一通り揃っているため、安心して就職活動を進めることができます。転職後のフォロー体制も整っており、入社後も定期的な相談が可能です。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
基本的に、dodaチャレンジでは「障がい者雇用枠」での求人紹介を中心に行っているため、障がい者手帳を所持していることが前提となるケースが多いです。そのため、現時点で手帳を持っていない場合は、求人の紹介が難しいことがあります。ただし、手帳を申請中である場合や、医師からの診断がある場合などは、状況に応じて面談や相談が可能な場合もあります。まずは、申請予定の有無や現状について担当者に率直に伝えることが大切です。体調や障がいの状況が安定していない場合は、就労移行支援などの利用を提案されることもあります。いずれにしても、焦らず準備を整えてからの再相談が望ましいです。
関連ページ:dodaチャレンジは手帳なしで利用できる?障害者手帳は必須!申請中でも利用できます
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジでは、障がいの種類で「登録できない」と明確に制限しているわけではありませんが、サポートの対象になるかどうかは状況によって異なります。たとえば、障がい者手帳を持っていない場合、または手帳があっても就労が現時点で難しいと判断された場合には、サポート対象外となることもあります。また、就労経験がまったくない方や、長期間のブランクがある方などは、まずは就労訓練や就労移行支援の利用を案内されるケースもあります。精神障がいや発達障がいのある方についても、体調や就労準備の状況によって判断されるため、登録できるか不安な場合は、事前に問い合わせてみるのがおすすめです。まずは今の状態を正直に伝えて、どのようなサポートが可能かを確認してみましょう。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジを退会したい場合は、担当のキャリアアドバイザーへ連絡するのが基本的な流れです。直接メールや電話で「退会希望」と伝えれば、個別に手続きを進めてもらえます。退会時には、理由を簡単に聞かれることもありますが、強く引き止められることはほとんどありませんので安心してください。また、登録していた個人情報は退会後に削除されますが、一度退会してしまうと再登録の際にはすべての情報を新たに入力する必要があります。今後また利用する可能性がある方は、いったん「サポート休止」として登録情報を残しておく方法も選べます。転職活動を一時中断したいだけであれば、アドバイザーにその旨を伝えると、柔軟に対応してもらえることが多いです。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、基本的にオンラインで実施されています。遠方にお住まいの方や外出が難しい方でも、自宅からPCやスマホを使って参加できるため、とても利用しやすい仕組みです。Zoomや電話を使って、アドバイザーと1対1でじっくり話をすることができ、現在の状況や今後の希望、配慮してほしい点などを丁寧に聞いてくれます。オフィスに出向く必要がないため、地方在住の方や体調に不安のある方にとっても安心です。面談の所要時間はだいたい30分~1時間ほどで、日程も自分の都合に合わせて予約できます。初回のカウンセリングでは履歴書などがなくても問題ありませんので、まずは気軽に相談してみるのがおすすめです。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジには、公式には年齢制限は設けられていません。何歳であっても登録そのものは可能です。ただし、実際にサポートや求人紹介の中心になっているのは20代〜50代前半の方であることが多く、年齢が上がるにつれて紹介される求人の数が限られてくる傾向はあります。特に50代後半以降になると、体力的な面や企業側の採用ニーズとの兼ね合いから、求人が見つかりにくくなることもあるため、状況に応じてハローワークの障がい者専門窓口や地域の就労支援センターと併用するのが有効です。年齢に関係なく「自分の特性や希望に合った働き方」を実現するためには、複数のサポート先を利用することが安心につながります。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
はい、離職中の方でもdodaチャレンジのサービスを問題なく利用することができます。実際、転職や再就職を目指して登録される方の多くが現在離職中です。面談では、離職している理由や現在の体調、再就職に向けた不安などについても丁寧にヒアリングしてくれるため、今の状況を正直に伝えることで、無理のない求人を紹介してもらいやすくなります。また、ブランクがある場合でも、「何をしていたか」「これからどう働きたいか」を明確にすることで、選考に進むチャンスが生まれます。働く準備が整っていない場合でも、就労移行支援の利用など、今後に向けたサポートを提案してもらえることもあるので、安心して相談してみてください。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは、基本的には社会人向けの転職・就職支援サービスとなっており、いわゆる「就活生(新卒)」に特化したサービスではありません。そのため、大学生や専門学生などでこれから就職活動を始めるという方には、dodaチャレンジよりも「新卒向け就活エージェント」や「学校のキャリアセンター」「ハローワーク新卒窓口」などの利用が適しています。ただし、既卒で就職活動を続けている方や、障がい者雇用枠での就職を希望している学生の方については、状況に応じて相談が可能なケースもあります。もし在学中でも就職への不安が強い、サポートが必要と感じる場合は、まずは一度問い合わせてみるのがおすすめです。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスと比較
dodaチャレンジは障がいのある方に特化した就職・転職支援サービスとして多くの実績を持っていますが、「登録したのに求人を紹介してもらえなかった」「希望条件に合う仕事がないと言われた」という声も一部にはあります。実際には、体調や働き方の希望、障がいの特性によっては、一時的にマッチする求人が見つからず、紹介を見送られるケースもあるのが現実です。ですが、これはdodaチャレンジに限らず、他の障がい者向けエージェントでも同様のことが起こり得ます。
たとえば、atGPやラルゴ、ウェルビーなど他の支援サービスも、それぞれ得意な業種や支援対象が異なり、紹介の可否は状況によって左右されます。在宅勤務に強いサービス、若年層の支援に力を入れているサービスなど、特徴がはっきり分かれているため、自分の希望や状態に合ったサービスを選ぶことがとても大切です。
「断られた=自分に問題がある」ではなく、「今の条件に合う求人が一時的に見つからなかった」というだけのことも多いです。複数のサービスを併用しながら、状況に合う支援先を見つけていくことで、可能性はぐっと広がります。焦らず、まずは相談できる場所を増やしてみることが、第一歩につながります。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー(atGP) | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビパートナーズ紹介 | 350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援・ミラトレ | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッドチャレンジ | 260 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、東海、福岡 | 全ての障害 |
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談まとめ
dodaチャレンジに登録したものの、「紹介できる求人がないと言われた」「サポート対象外ですと断られた」といった経験をした方もいます。せっかく勇気を出して相談したのに、断られると落ち込んでしまいますよね。でも、実はその理由の多くは「あなた自身が悪いから」ではなく、タイミングや条件、体調や希望内容とのミスマッチによるものです。
たとえば、希望条件が厳しすぎたり、障がい者手帳が未取得だったり、働ける時間や地域が限られていたりすると、エージェント側が「紹介できる求人が今はありません」と判断することがあります。また、精神的な安定や就労経験がまだ整っていない場合には、まずは就労移行支援などの別のサポートを案内されることもあります。
ここでは、実際に「断られてしまった」と感じた方々の体験談をもとに、どんな理由で紹介が難しかったのか、そしてその後どう対処したのかを具体的に紹介しています。「自分だけがダメだったわけじゃない」と知ることで、少しでも前向きに次のステップに進むヒントになればうれしいです。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット